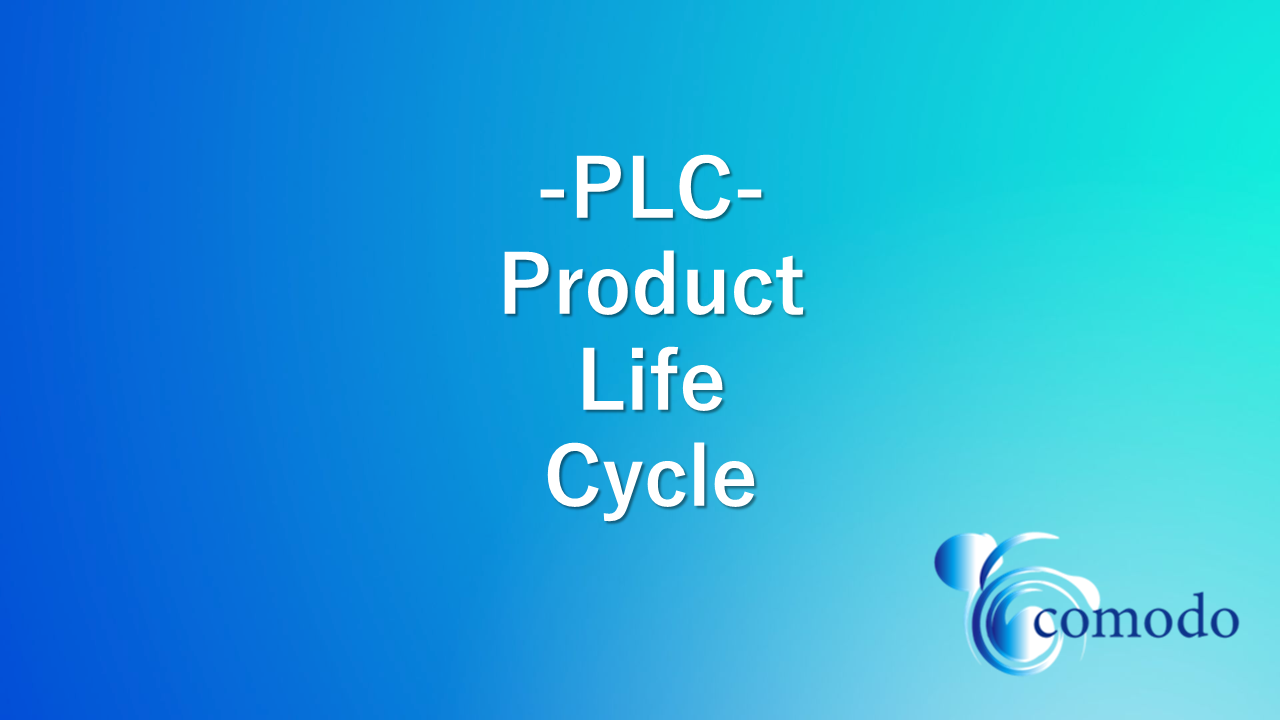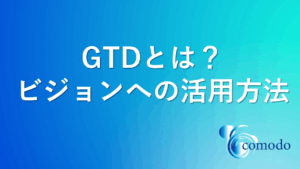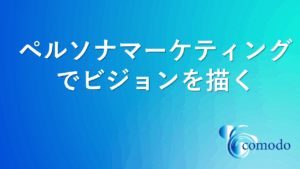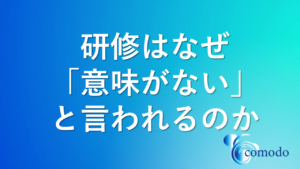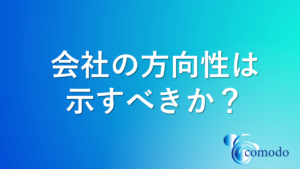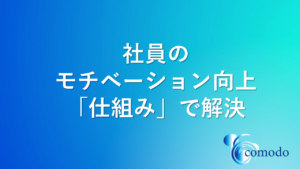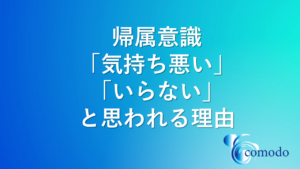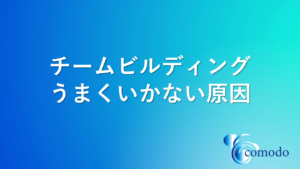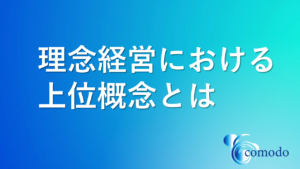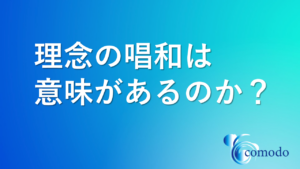製品には寿命があります。
売れ行きの好調な商品であっても、必ずどこかのタイミングで需要は頭打ちとなり、やがて衰退していきます。
こうした製品のライフサイクルを4つのステージに分けて考えるのが「PLC(Product Life Cycle)」という考え方です。
この記事では、PLCの各ステージの特徴と、マーケティング・事業戦略上の活用方法を解説します。
さらに記事の後半では、PLCの考え方をビジョン策定にどう応用できるかについても掘り下げていきます。
PLCの基本:4つの時期
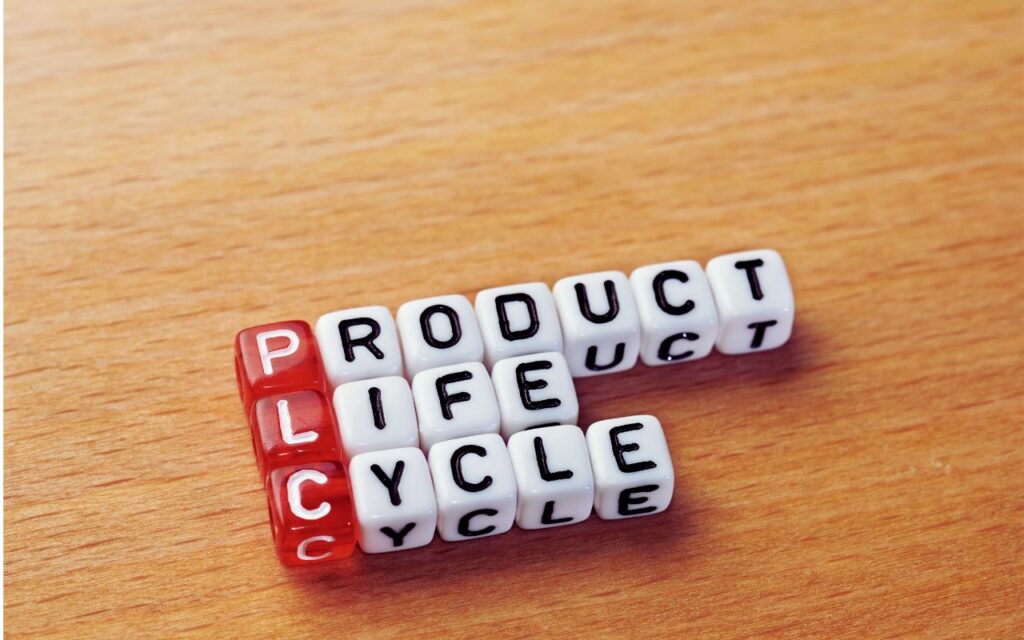
PLCの基本は、以下の4つの時期に分けられます。
- 導入期
- 成長期
- 成熟期
- 衰退期
上記の4つの流れに対して、戦略を検討していく必要があります。
以下では、それぞれの期の特徴について解説します。
導入期:製品を「認知」してもらうことが最優先
PLCの最初のステージは「導入期」です。
この時期は、製品が市場に出て間もない段階であり、消費者にとってはまだ知られていない存在です。
売上は小さく、費用も多くかかるため、利益はほとんど期待できません。
ここでは、広告やプロモーション、販路開拓など「認知向上」に向けた活動が重要になります。
革新的な商品であれば、製品カテゴリーそのものの認知を広げる啓蒙活動が必要になることもあります。
特にスタートアップ企業や新規事業では、この導入期をどう乗り越えるかが勝負所になります。
成長期:一気に売上を伸ばすタイミング
製品が市場に浸透し、ユーザーの認知が進むと「成長期」に入ります。
この段階では売上が大きく伸び、マーケットが急拡大していきます。
他社もこのタイミングで参入してくるため、競争が始まる時期でもあります。
成功の鍵は「差別化」と「供給力の強化」です。
販売体制やサービス体制を整え、製品をしっかり届ける準備が求められます。
また、模倣される前に技術やブランドの優位性を築くことで、他社よりも高いシェアを確保できます。製品ラインの拡張や関連サービスの開発も有効です。
成熟期:競合が増え、差別化の再構築が求められる
市場が飽和し、売上の成長が鈍化してくると「成熟期」に入ります。
多くの競合が出揃い、価格競争や機能の似通いが起きる時期です。
ここでは「顧客の囲い込み」や「コスト効率化」「ブランディング」が戦略の主軸となります。
また、今後の衰退期を見据えて、製品の改良・アップデートや新製品への橋渡しとなる戦略も検討すべきです。
成熟期での手を打たずに時間が経てば、そのまま急速な売上減少へつながってしまいます。
衰退期:終わらせるのか、延命させるのかを判断する
売上が大きく下がり、顧客の関心も薄れてくると「衰退期」に入ります。
このステージでは、新しい製品が登場して顧客の需要が移り、既存製品は徐々に見向きされなくなっていきます。
この時期に必要なのは、「撤退」か「延命」かの判断です。
利益が確保できる間はコストを最小限に抑えて販売を続けるのも一つの戦略ですが、新規製品へ経営資源を移すことも重要な選択肢になります。
衰退期でも利益率を維持するためには、生産・流通体制の簡素化や販路の絞り込みが必要です。人気が一部に根強く残るような製品であれば、ニッチ戦略で延命を図る余地もあります。
PLCをビジョン策定に応用する考え方

ここまで見てきたように、PLCは製品や事業の「今の立ち位置」を見極めるうえで非常に有効なフレームワークです。
では、これをビジョン策定にどう活かせるのでしょうか。
以下でビジョン策定に応用する考え方について解説します。
現在地を知ることで「これから」の方向性が見える
ビジョンは未来の理想像ですが、そこにたどり着くには「いまどこにいるか」を知ることが必要です。
PLCのステージごとに課題や必要な打ち手が違うように、ビジョンの実現も今いるフェーズによって取るべき行動が変わります。
たとえば、導入期にいる企業が「業界トップを目指す」と掲げても、現実味がありません。
まずは認知を高め、ユーザーの声を集め、製品価値を磨くことから始めるべきです。
逆に、成熟期の企業なら「顧客との長期的関係を再定義する」などの未来像が現実的になります。
製品寿命と企業寿命をリンクさせて戦略を立てる
自社の主力商品がすでに成熟期や衰退期に入っているのであれば、将来的な収益減を見越して新たな成長の柱を用意しなければなりません。
PLCは一つひとつの製品だけでなく、事業ポートフォリオ全体に広げて活用することで、企業の長期ビジョンにもつながります。
特に中長期的な事業計画や経営戦略においては、どの製品群に資源を集中させ、どこを切り離すかの判断が必要です。
PLCを軸にすれば、冷静かつ客観的にその判断を下すことができます。
変化に強い組織づくりの視点としても活用できる
PLCは「変化すること」が前提のモデルです。
そのため、変化への柔軟さ・スピード感を備えた組織文化とセットで考えることが求められます。
時代の変化や市場の変化に合わせて、ビジョンを柔軟に見直す仕組みも大切です。
一度掲げたビジョンを守るだけではなく、「今、どのステージか」を定期的に見直し、必要に応じて更新していく。そんな柔軟な姿勢が、持続的成長につながります。
PLCを使って「現実的なビジョン」を描く

PLCは製品の寿命を理解するためのフレームワークですが、それは同時に「現状を把握し、未来を考える」ための視座でもあります。
自社が今どこに立っているのか、どの事業が伸び、どこに陰りが見えているのか。
それを冷静に見極めたうえで、実現可能なビジョンを描くことが求められます。
ビジョンは夢を語るだけではなく、現実の積み重ねによって実現されていくものです。
弊社もビジョン策定のサポートを行っておりますので、ぜひビジョンの策定・見直しを検討する際にはご相談ください。

株式会社comodo
石垣敦章(イシガキ ノブタカ)