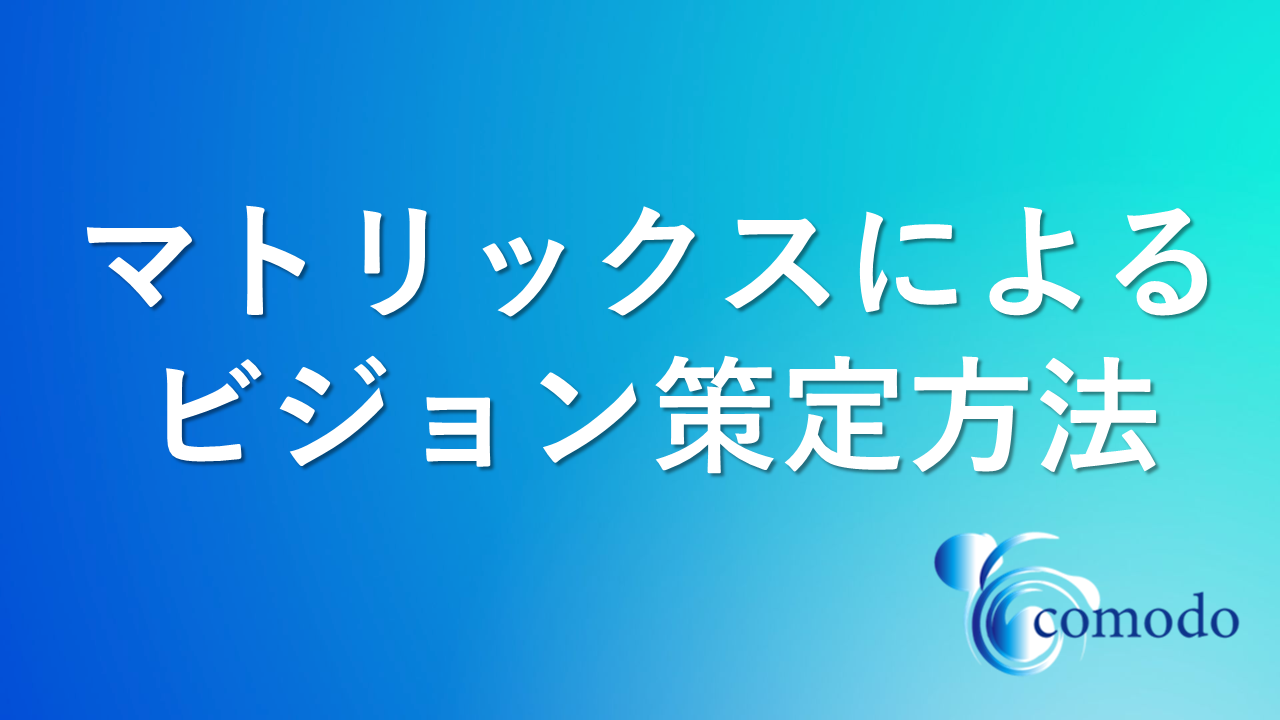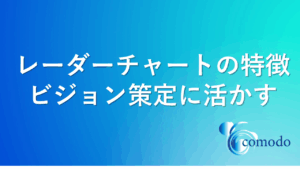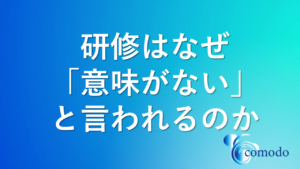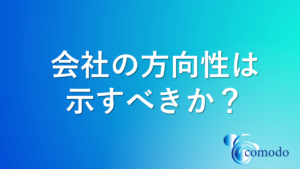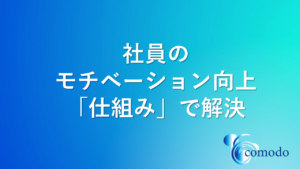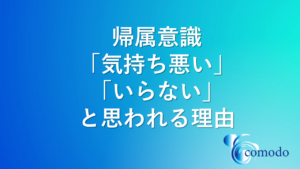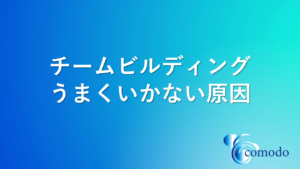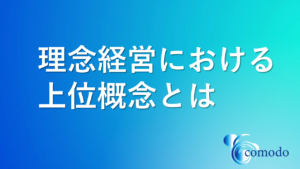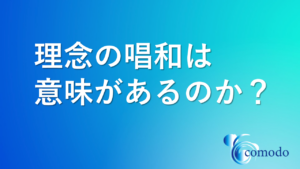マトリックスは、ビジネスの現場で最も汎用性が高く、理解しやすいフレームワークの一つです。
2つの軸(行と列)を使ってデータや評価項目を整理することで、複雑な情報の比較や分析が視覚的に行えるのが最大の特徴です。
表形式で情報を整理するこの考え方は、日々の意思決定から戦略立案まで幅広く応用できます。
本記事ではマトリックスの基礎を押さえたうえで、ビジョン策定への応用についても掘り下げます。
マトリックスの基本構造と使い道
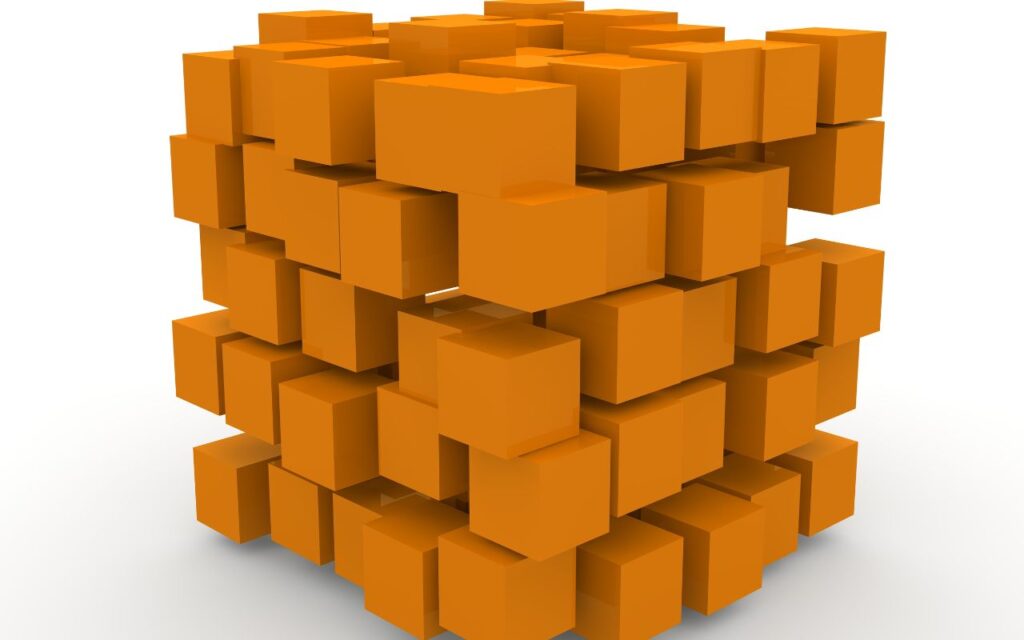
マトリックスは、「縦に並ぶ項目」と「横に並ぶ要素」を交差させて、評価・分類・数値の整理を行う表です。
たとえば、以下のような場面で使われます。
- 複数の商品を、価格・機能・デザインなどの観点で比較する
- 顧客層ごとに満足度や購買頻度を整理する
- 各部署と目標項目を組み合わせてKPIを可視化する
一見ただの表に見えますが、論理的に軸を設計することで、情報の関連性や優先度が一目で把握できるようになります。
実際のマトリックスの設計例
以下のように、商品の機能別評価を整理したマトリックスはとても実用的です。
| 商品名 | 価格 | 機能 | デザイン | 耐久性 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品A | 85 | 60 | 60 | 80 | 285 |
| 商品B | 76 | 64 | 60 | 54 | 254 |
| 商品C | 86 | 88 | 40 | 30 | 244 |
| 商品D | 65 | 58 | 40 | 40 | 203 |
| 商品E | 75 | 80 | 60 | 70 | 285 |
このように情報を配置すると、「合計点の高い商品は?」「価格と機能のバランスが良いのは?」といった問いに対して直感的に答えが見えてきます。
マトリックス作成の3つのポイント

マトリックスを効果的に活用するには、単に表を作るだけではなく、情報を「どう見せるか」「何を比較するか」という設計の意図が重要です。
ここでは、使いやすく、判断に役立つマトリックスを作成するための基本的なポイントを3つに絞って解説します。
目的に合った軸を選ぶ
マトリックスの軸は、比較したい観点や判断材料に応じて決める必要があります。
商品なら「価格・品質・デザイン」、顧客なら「属性・購買頻度・満足度」など、論点が明確になる軸を選ぶことで、分析がしやすくなります。
情報の粒度をそろえる
数値で比較する場合は、すべてを同じスケールで評価することが重要です。
たとえば100点満点評価で統一する、星の数で換算するなど、視覚的に比較しやすくします。
見やすさを意識してレイアウトする
行や列が多くなると可読性が落ちるため、
- 項目数を必要最低限に絞る
- 背景色を変える
- 重要な箇所を太字にする
など、ビジュアル面での工夫も大切です。
見やすいマトリックスほど、他人にも共有しやすく意思決定に役立ちます。
マトリックスの活用例と効果
実際のビジネスシーンで、マトリックスは以下のような効果を発揮します。
- 商品ラインナップの棚卸しとポジショニングの整理
- チームメンバーとタスクの関連性・役割分担の可視化
- マーケティング施策のチャネル×ターゲット別効果の分析
- 各事業部と戦略KPIとの整合性チェック
多くの情報を頭の中だけで比較しようとすると混乱しがちですが、マトリックスに落とし込むことで、関係性やバランスを俯瞰して見ることが可能になります。
マトリックスを応用したビジョン策定の考え方

ここからは、マトリックスの思考を応用して「ビジョン策定」に役立てる方法について解説します。
ビジョンというと抽象的な言葉になりがちですが、「整理して考える」「関係性を構造化する」というマトリックスの視点を導入することで、具体性と納得感が大きく高まります。
関係者とビジョン要素のマトリックスをつくる
たとえば、社内の関係者(経営層・現場・顧客・地域・取引先)を縦軸に、ビジョンに含めたい要素(社会貢献・成長・ブランド・収益性など)を横軸にとります。
| 社会貢献 | 成長 | ブランド | 収益性 | |
|---|---|---|---|---|
| 経営層 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ |
| 現場社員 | △ | 〇 | ◎ | △ |
| 顧客 | ◎ | △ | 〇 | × |
| 地域 | ◎ | × | △ | × |
このように関係性を整理することで、「誰の視点に配慮する必要があるか」「ビジョンの中で何を強調すべきか」が可視化されます。
複数のビジョン候補を比較するマトリックス
ビジョン候補が複数ある場合、それぞれを軸にして「実現可能性」「伝わりやすさ」「社員の共感度」などの観点で比較するマトリックスを作成します。
| ビジョン案 | 実現可能性 | 共感度 | 社外への発信力 |
|---|---|---|---|
| ビジョンA | ◎ | △ | 〇 |
| ビジョンB | 〇 | ◎ | ◎ |
| ビジョンC | △ | 〇 | △ |
この比較表があることで、社内の合意形成がスムーズになります。
抽象的な「なんとなく良さそう」から一歩踏み込んで、「どのビジョンが軸としてふさわしいか」を論理的に検討できるようになります。
ビジョンの定着率を測るためのマトリックス
ビジョンは「策定する」ことがゴールではなく、「浸透し、行動に影響を与える」ことが重要です。
そのため、各部門やチームにおけるビジョンの理解度・共感度・行動への反映度をマトリックスでチェックすることも有効です。
| 部署/評価項目 | 理解度 | 共感度 | 行動反映 |
|---|---|---|---|
| 営業部 | ◎ | 〇 | 〇 |
| 開発部 | 〇 | △ | △ |
| 経営企画部 | ◎ | ◎ | ◎ |
数値化が難しい感覚的な評価も、こうした整理で傾向を把握でき、フォローアップの判断に役立ちます。
マトリックスは「考える道具」としての基本

マトリックスは、単なる表計算の手段ではなく、「物事の関係性を整理し、全体像を見通すための思考法」です。
その汎用性とシンプルさは、あらゆる情報整理・戦略設計・チーム共有において強力な味方となります。
そして、ビジョン策定という本質的な経営活動にも、マトリックスの構造化思考は大きく貢献します。
「何を」「誰に向けて」「どう位置づけるのか」を可視化することで、感覚ではなく合意と行動を生むビジョンが生まれるのです。
弊社でもビジョンの策定をしておりますので、マトリックスなども用いながら思考を整理してみましょう。
そのほか、ビジョンの策定でお困りでしたら、ぜひご相談ください。

株式会社comodo
石垣敦章(イシガキ ノブタカ)