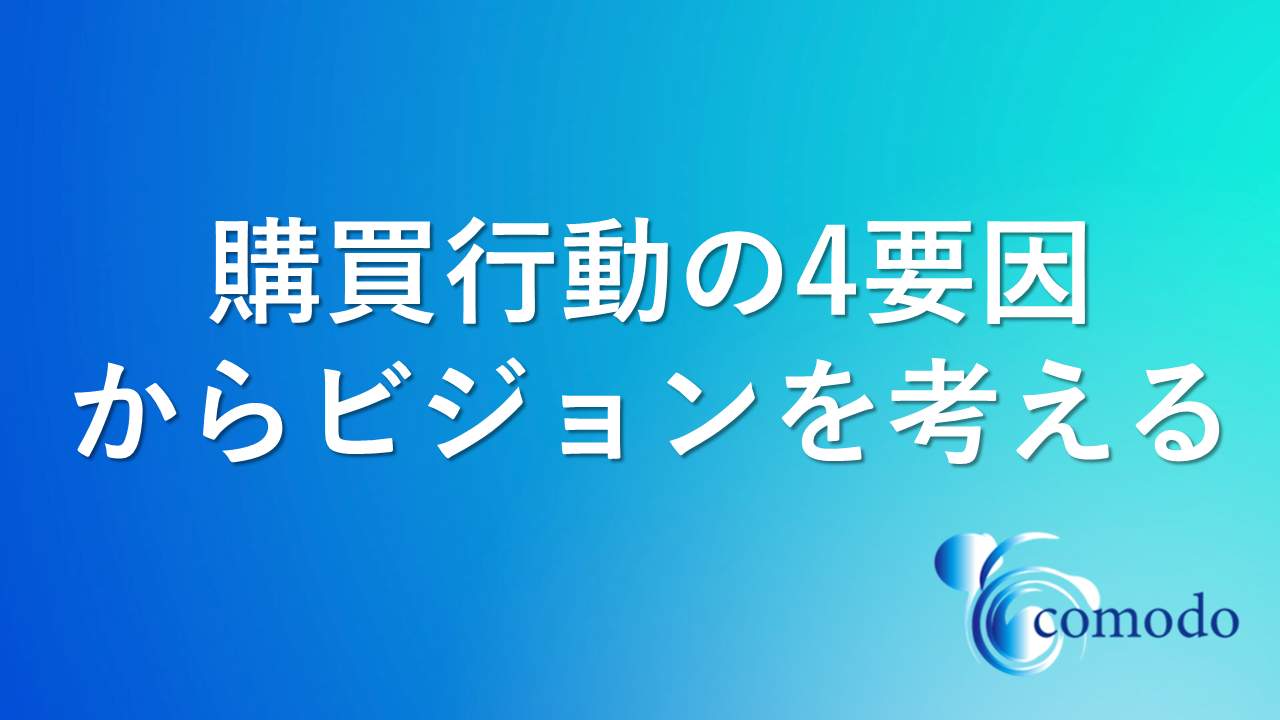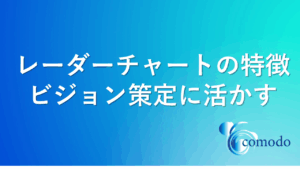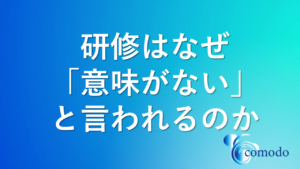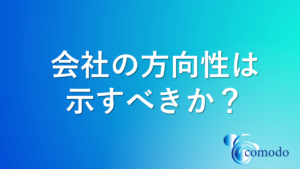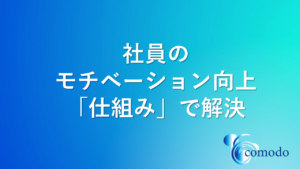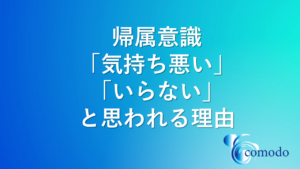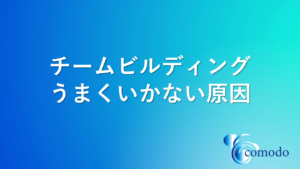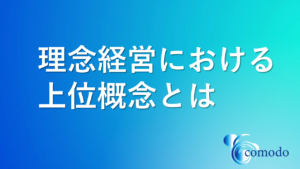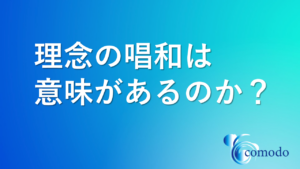購買行動とは、人が商品やサービスを購入する際の意思決定プロセスです。
この行動には無数の要素が絡んでいますが、フィリップ・コトラーによるフレームワークでは、それらを4つの主要な要因に分類して整理することができます。
本記事では「文化的要因」「社会的要因」「個人的要因」「心理的要因」という4分類を起点に、マーケティングやターゲット設定における活用方法を解説します。
さらに、ビジョン策定に応用する考え方についても後半で紹介します。
文化的要因:最も深層にある影響力
文化的要因は、個人の購買行動に最も根深い影響を与える要素です。
人は生まれ育った文化圏や風土、宗教観、社会階層によって「何を良しとするか」「何を避けるか」といった基本的な価値観を身につけます。
たとえば、贈り物の文化ひとつとっても、欧米では誕生日にパーティとプレゼントを贈ることが一般的ですが、日本ではお歳暮やお中元などの季節行事の方が重視されます。
このような文化背景は、購買タイミングや対象商品に大きく影響します。
さらに、社会階層(いわゆる階級や所得水準)も文化的要因に含まれます。
同じ文化圏でも、高所得層と低所得層とではブランド選好や支出の優先順位が異なるのです。
社会的要因:身近な人間関係からの影響
社会的要因とは、「家族・友人・職場・近隣コミュニティ」といった周囲の人間関係によって形成される影響のことです。
日常の中で頻繁に接する人々の考え方や評価が、購買選択に大きく関わることがあります。
たとえば、職場の同僚があるガジェットを使って高評価していれば、自分も試してみようという動機が生まれます。
また、子育て世代であれば、ママ友との会話から人気の商品や情報を知る機会が多くなります。
このように、「社会的承認」や「共通体験」の要素が購買の背中を押すのが、社会的要因の特徴です。
企業が口コミやSNSでの評価を重視する理由は、まさにここにあります。
個人的要因:ライフステージと価値観の個性
個人的要因は「年齢・職業・経済状態・家族構成・ライフスタイル」といった、個人の属性や状況に基づく要素です。
たとえば、同じ商品であっても大学生と定年退職者ではニーズも期待も異なります。
また、価値観やパーソナリティによっても違いが出ます。
例えば、「効率」を重視する人は時短グッズに惹かれやすく、「感性」を重視する人はデザイン性やブランドイメージを重要視します。
企業がペルソナ(想定顧客像)を設定する際に、この個人的要因が最も重要な分析ポイントになります。
心理的要因:意思決定を左右する内的動機
心理的要因は、「動機・信念・態度・学習」といった内的な心理プロセスによる影響です。
商品への期待、ブランドへの信頼、あるいは過去の成功体験や失敗体験などが、購買意欲を左右します。
たとえば、「健康になりたい」という動機を持つ人は、健康食品や運動器具に対して高い関心を持ちます。
その動機が「過去に病気を患ったことによる不安」から来ているなら、より強い動機づけとなるでしょう。
ブランドへの信頼が高まれば、価格が多少高くても購入する傾向が見られます。
このような「安心感」「納得感」といった感情の動きが心理的要因にあたります。
4要因は複合的に作用する
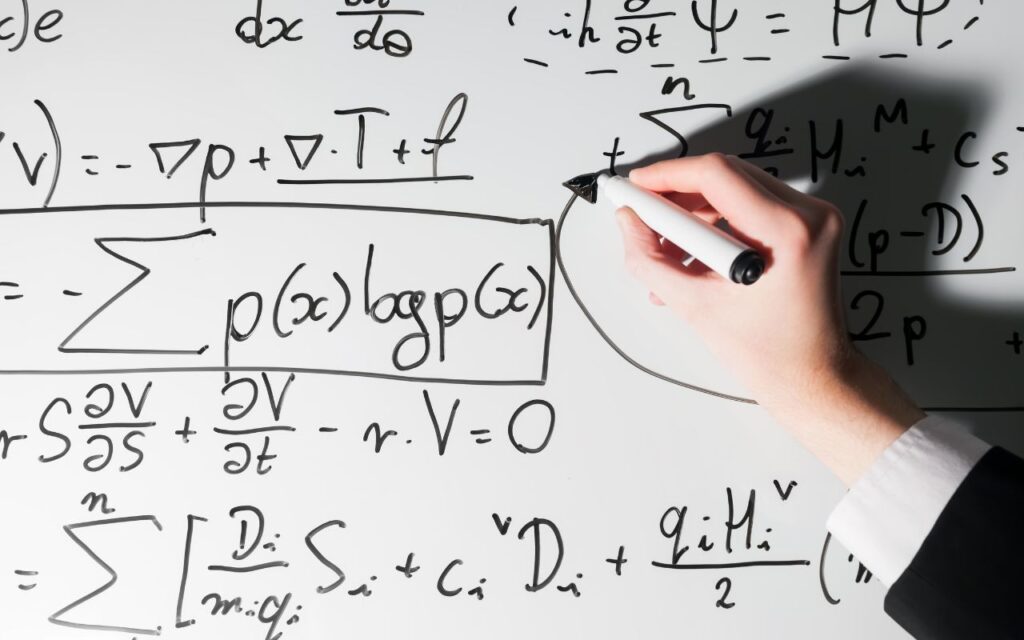
実際の購買行動では、上記4要因のうち1つだけが働くわけではありません。
たとえば、健康志向のヨーグルトを購入する人の場合であれば、以下のようになります。
- 文化的要因:健康を重視する国民性
- 社会的要因:友人の口コミや職場での話題
- 個人的要因:高齢の親の健康を気遣うライフステージ
- 心理的要因:罪悪感なく間食したいという感情
これらが複雑に絡み合って、最終的な購買につながります。
企業が施策を検討する際には、どの要因が特に影響を与えているのかを分析し、優先順位をつけて対応する必要があります。
購買行動の4要因をビジョン策定に応用する
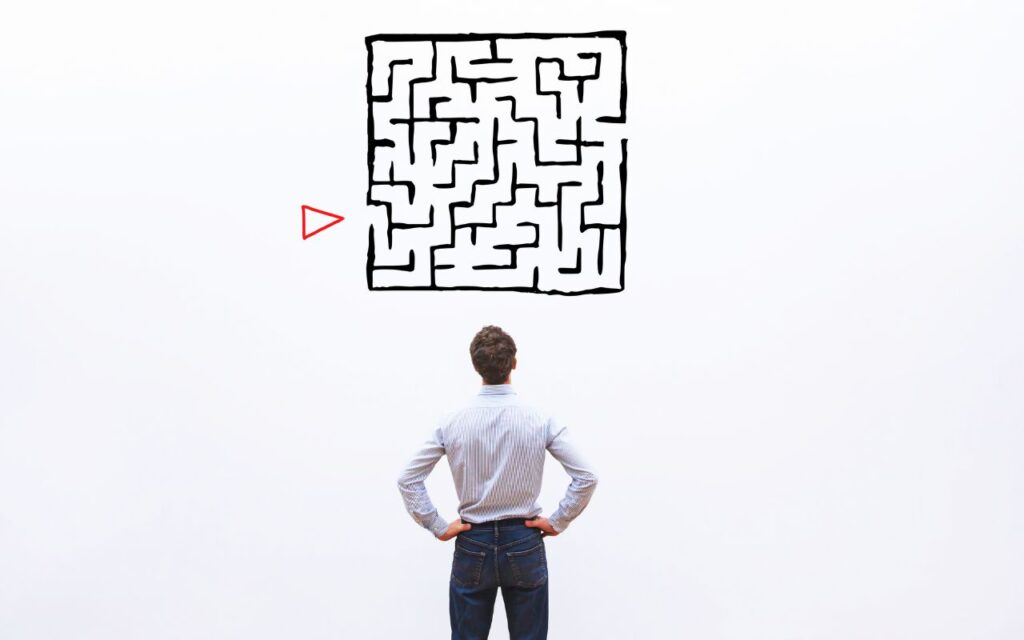
購買行動の4要因は、マーケティングだけでなく、企業の中長期的なビジョン策定においても応用可能です。
なぜなら、ビジョンとは顧客の未来の価値観やニーズに応えるための方向性だからです。
以下で「購買行動の4要因」とビジョンの関係性について解説します。
文化的要因から未来の市場変化を読み取る
企業ビジョンを描くうえで、社会の文化的潮流の変化を捉えることは重要です。
たとえば、「サステナビリティ」「多様性の尊重」「ウェルビーイング」など、現代の文化的価値観の変化をビジョンに組み込むことで、企業はより共感を得られる存在になります。
社会的要因から共感の輪を設計する
ビジョンは、単に経営陣が掲げるものではなく、社会や顧客と共に共有する必要があります。
誰とどのような共感関係を築くかを考えるうえで、社会的要因の視点は有効です。
たとえば「地域に根差す」「教育支援で世代をつなぐ」といった社会との関係性を描くことがビジョンの浸透につながります。
個人的要因から具体的なペルソナに落とし込む
将来のビジョンを描く際には、そのビジョンが応えるべき「顧客の個人像」を明確にする必要があります。
年齢、職業、ライフスタイルなど、個人的要因を踏まえてペルソナを設計すれば、より具体的でリアリティのあるビジョンになります。
心理的要因から情緒的な訴求を盛り込む
強いビジョンには「情緒」があります。
どんな世界を目指すのか、なぜそれが大切なのかという背景に、顧客や社会の心理的要因を織り込むことで、心を動かすストーリーが生まれます。
「不安を希望に変える」「自分ごと化できる未来を描く」など、感情に訴える要素を加えることが鍵となります。
人の購買行動からビジョンを考えてみる

購買行動の4要因は「文化・社会・個人・心理」という視点から顧客を立体的に理解するためのフレームワークです。
マーケティング戦略においてはもちろん、企業のビジョン策定においても、これらの要因を意識することで、より共感性のある未来像を描くことが可能になります。
人がモノを選ぶ背景には、必ず理由があります。
その構造を理解し、活用することこそが、顧客と社会から選ばれる企業になるための一歩です。
ビジョンの策定においては、弊社でもサポートしております。
さまざまな観点からビジョンを策定しますので、ぜひ新しくビジョンを策定したい企業またはビジョンを見直したい企業は、ぜひご相談ください。

株式会社comodo
石垣敦章(イシガキ ノブタカ)