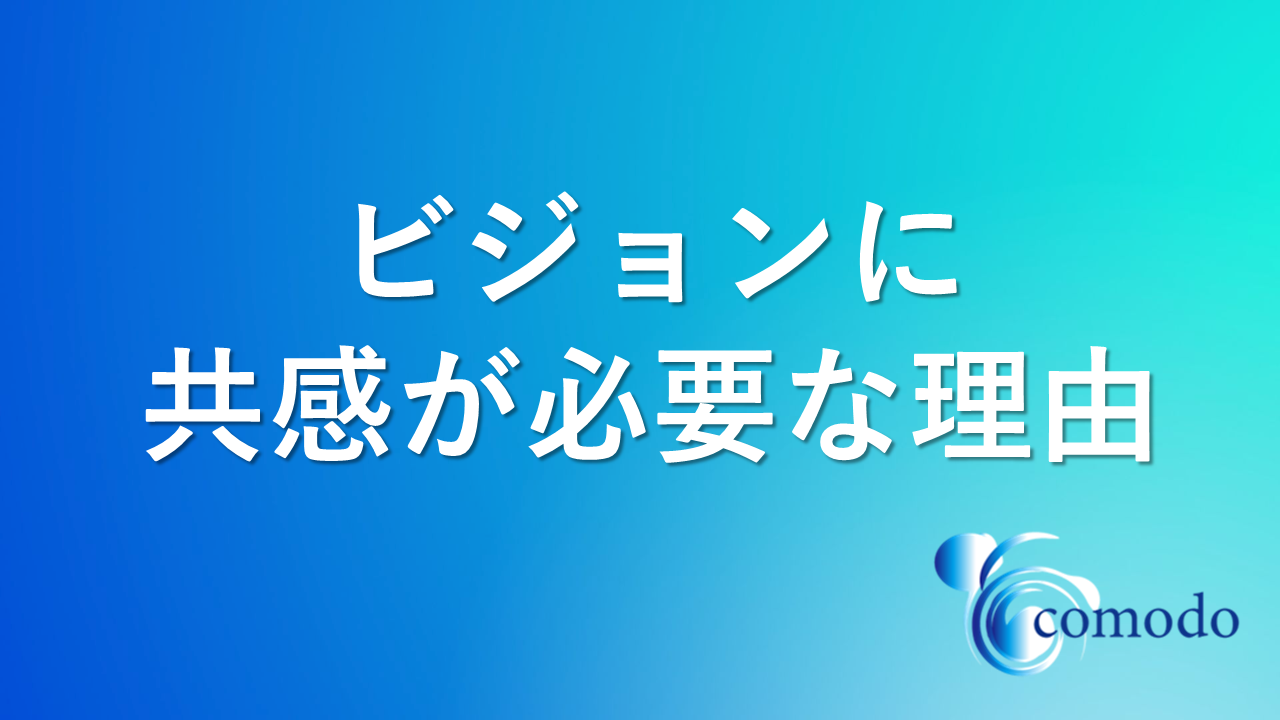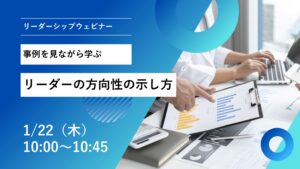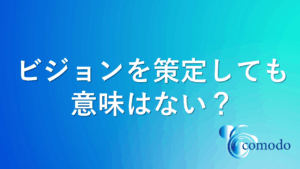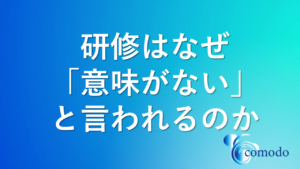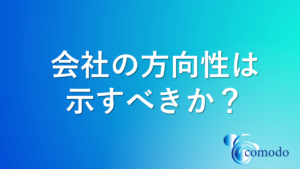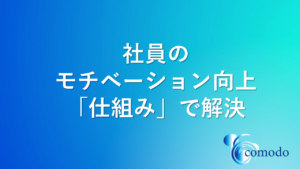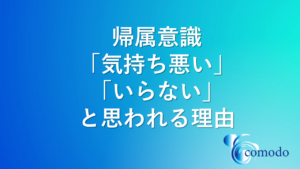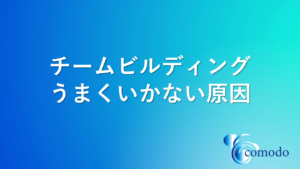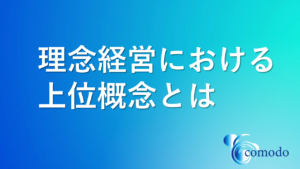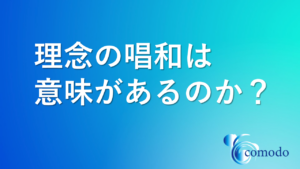社員がビジョンに共感できるかどうかは、組織の一体感や推進力に直結します。
共感があれば、社員は自らの役割を主体的に考え、迷いなく行動できます。
逆に共感がなければ、ただ業務をこなすだけになり、現場の熱量や創意工夫は生まれません。
たとえば、新しい挑戦や変化が求められる場面でも、共感が浸透していれば困難を乗り越える力が強まります。
以下では、「ビジョンに共感」がなぜ組織づくりに欠かせないのかを整理します。
共感を得られないビジョンが組織にもたらす課題
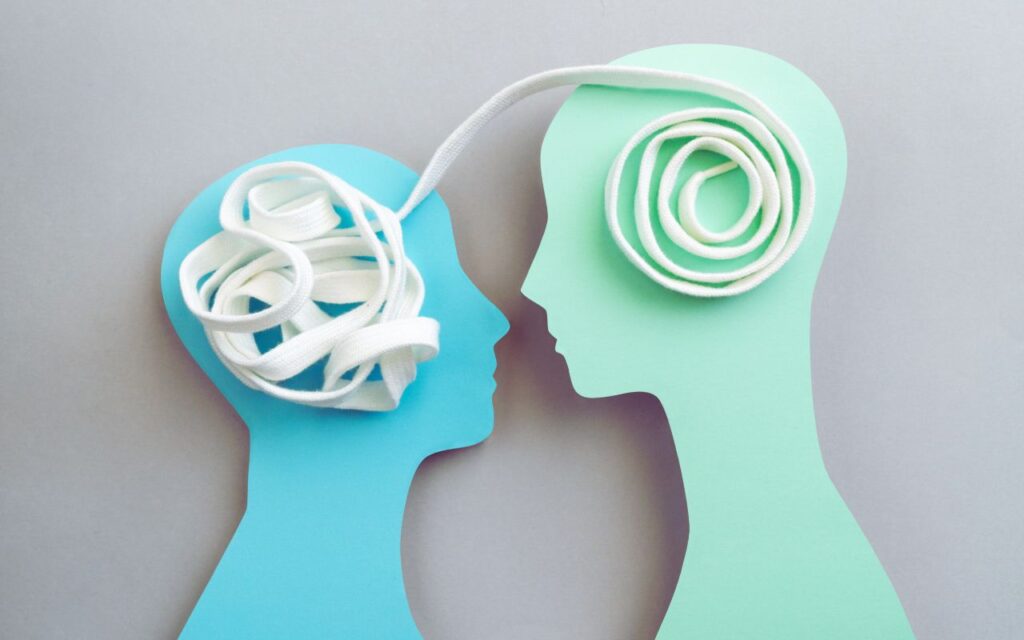
ビジョンに共感できない場合、社員の受け止め方がバラバラになり、組織全体の動きにまとまりが生まれません。
現場の温度差や施策の形骸化が進み、やがて離職やエンゲージメント低下などの課題も表面化します。
経営層の想いだけが先行して、現場との距離が広がると、せっかくの戦略や制度も成果につながりにくくなります。
以下では、ビジョン共感の欠如が引き起こす具体的な課題を解説します。
現場での受け止め方がバラバラになる
ビジョンが現場の言葉や業務と結びついていないと、社員ごとに解釈が異なります。
たとえば、「成長」という言葉でも、何を目指せばいいのか現場ごとにイメージがズレてしまいます。
その結果、同じ会社にいても目指す方向が揃わず、組織全体の力が分散します。
共感されないビジョンは、現場の一体感を弱める要因となるのです。
施策や制度が形骸化するリスク
ビジョンに共感できていない組織では、制度や施策も表面的になりがちです。
たとえば、「お客様第一」を掲げていても、現場がその意味や意義を感じられなければ、形だけのスローガンに終わってしまいます。
目標や評価制度も「やらされ感」につながりやすく、組織の成長を妨げる要因となります。
離職やエンゲージメント低下につながる
ビジョンに共感できない環境では、社員のモチベーションが低下しやすくなります。
自分の働く意味が見えないままでは、やりがいや成長実感も得にくくなります。
その結果、離職やエンゲージメントの低下というかたちで組織の弱体化を招いてしまうのです。
「共感できるビジョン」とは何か
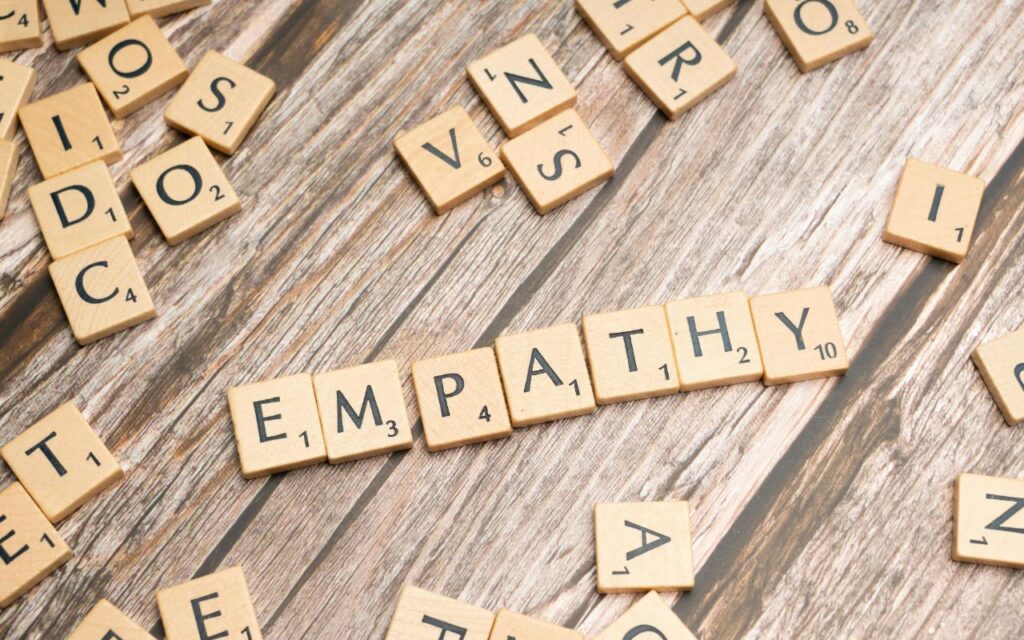
共感できるビジョンには、社員が自分ごととして捉えられる具体性や、現場目線・企業文化への一貫性があります。
言葉だけが先行するのではなく、日々の業務や価値観と自然につながる内容が必要です。
誰もが納得できる明確な方向性が、共感と行動の原動力となります。
以下では、「共感できるビジョン」とはどのようなものかを具体的に整理します。
自分ごと化できる具体性
ビジョンが日々の業務や自分の役割と結びつくことで、社員は自然と共感を持ちやすくなります。
たとえば「社会に貢献する」というビジョンも、自分の仕事がどのように社会に役立っているか実感できれば、行動に一貫性が生まれます。
曖昧な表現ではなく、具体的な言葉やストーリーが共感を引き出すのです。
現場目線・日常感との接続
現場が実感できる言葉や体験がビジョンに盛り込まれているかどうかも重要です。
たとえば、日常の業務で繰り返されるエピソードや成功事例がビジョンとリンクしていれば、現場にもすっと伝わります。
目の前の仕事やコミュニケーションの中で、ビジョンが「実感」できることが共感の土台になります。
企業文化や風土と矛盾しない一貫性
ビジョンは、その会社の文化や歴史、現場の価値観と矛盾がないことが求められます。
表面的なキャッチコピーだけでなく、これまでの組織の歩みや大切にしてきた考え方とつながっているビジョンは、社員にも自然に浸透します。
ビジョン共感を生むための工夫
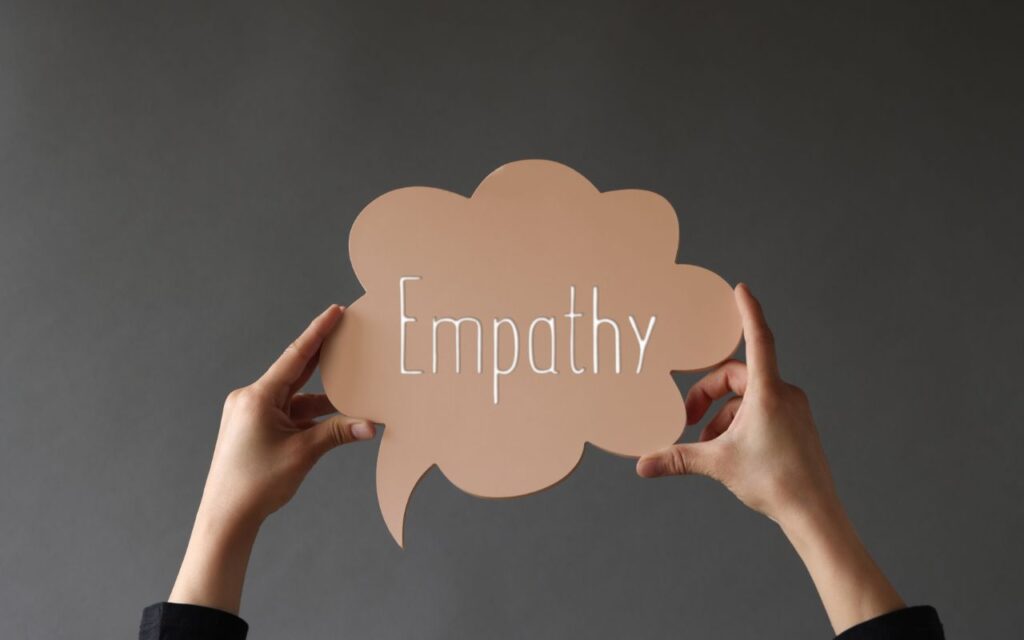
ビジョンへの共感を生むためには、経営層自らが想いや体験を語り、社員も対話や共創を通じて意見を出せる仕組みが不可欠です。
現場に届く具体的な言葉やストーリー、日常の仕組みとの連動が浸透を促します。
ビジョンを一方的に伝えるだけでなく、双方向の工夫がポイントです。
経営層自らのストーリーや体験を語る
経営層が自分の言葉でビジョンを語ると、社員の共感を呼びやすくなります。
たとえば、起業のきっかけや失敗談、現場でのエピソードを交えて話すことで、想いが伝わりやすくなります。
リアルな体験や熱意は、組織全体の一体感を生み出す原動力です。
社員を巻き込んだ対話・共創の場づくり
ビジョンは一方的に伝えるだけでなく、社員が意見を出し合える場を設けることで、納得感や自分ごと化が進みます。
たとえば、ワークショップやグループディスカッションを通じて、現場の声を吸い上げたり、一緒にビジョンの意味を考える機会をつくります。
参加意識が高まることで、共感も強まります。
現場に届く言葉と仕組みの設計
ビジョンを日々の業務や評価制度に組み込むことで、自然に意識しやすくなります。
たとえば、社内報や朝礼での共有、表彰制度との連動など、現場が触れる機会を増やすことで、言葉が浸透します。
仕組みとして定着させることが、共感の持続につながります。
ビジョンへの共感が組織の力を引き出す

ビジョンへの共感は、組織の理念や戦略を現場に根付かせる原動力です。
単なるスローガンではなく、一人ひとりが自分ごととして受け止められるかどうかが、組織の未来を左右します。
経営層から現場までが共通の価値観を持てたとき、個々の判断や行動が自然と組織目標に結びつきます。
一方で、表面的な伝達や一方通行のコミュニケーションでは、本当の共感は生まれません。
企業文化や日常の業務に根ざした実践と対話の積み重ねこそが、変化に強く柔軟な組織を育てる礎となります。
しかし、そもそものビジョンが伝わる形でなければ意味がありません。
弊社では、ビジョン・ブラッシュアップ研修をおこなっております。
「ビジョンが浸透しない」
「共感が生まれない」
という場合は、そもそものビジョンが上手くできていない可能性がありますので、ぜひご相談ください。

株式会社comodo
石垣敦章(イシガキ ノブタカ)