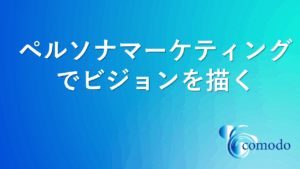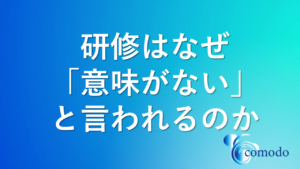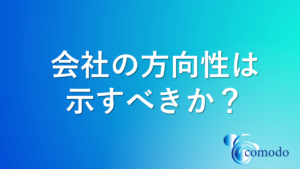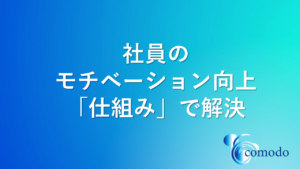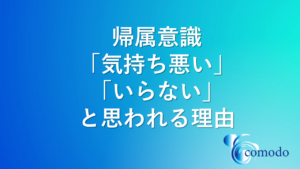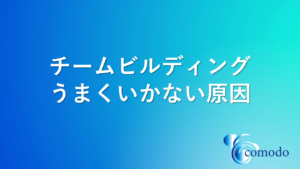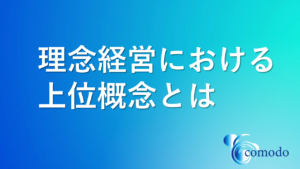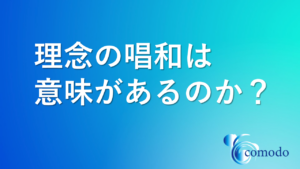広告や商品開発、店舗づくり、Webコンテンツ設計など、すべてのマーケティング活動に共通するのは、「人に行動を起こしてもらうこと」。
その起点となるのが「人の心の動き」です。
AIDMA(アイドマ)の法則は、消費者が商品やサービスを認知し、興味を持ち、最終的に購入に至るまでの心理的プロセスを5つのステップに分解したフレームワークです。
今回はそのステップをひとつずつ解説し、さらにビジョン策定にも役立つ思考法として応用していく方法をご紹介します。
AIDMAの5ステップ

AIDMAは1920年代にアメリカの広告学者サミュエル・ローランド・ホールが提唱した理論でありながら、現代の広告や販促の基礎にもなっています。
それぞれのステップは以下のように整理されます。
- Attention(注意)
- Interest(興味・関心)
- Desire(欲求)
- Memory(記憶)
- Action(行動)
一つひとつについて解説します。
Attention(注意)
どんなに優れた商品でも、知ってもらわなければ売れることはありません。
広告やSNS投稿、陳列、パッケージなど、まず視覚・聴覚・言葉などを通じて「気づき」を得ることが最初の一歩です。
この段階では、「目立つこと」「印象に残ること」が目的になります。
興味を持ってもらう以前に、そもそも選択肢のひとつとして候補に入れてもらう必要があるのです。
Interest(興味・関心)
一度目に入ったからといって、すぐに購入されるとは限りません。
人は気になったものについて、さらに情報を集めようとします。
このフェーズでは、「商品の特長」「価格」「レビュー」「使い方」などの情報が検索・比較されることが多いです。
企業側としては、具体的な魅力を伝えられるコンテンツや情報設計、丁寧な説明が必要です。
Desire(欲求)
情報を見たうえで、「自分の問題を解決できそう」「生活が豊かになりそう」と感じたとき、はじめて購買欲が生まれます。
ここで重要なのは、商品のベネフィット(利得)です。
スペックや性能だけでなく、「自分ごと」に置き換えたときのイメージが湧くように、「感情に訴える設計」が鍵になります。
Memory(記憶)
すぐに買わない人も多くいます。
たとえば「給料日まで待とう」「プレゼントとして検討しよう」など、いったん保留される場合があります。
そのとき、記憶に残っていなければ、機会損失が起こります。
「印象的なキャッチコピー」「使いやすい商品名」「リターゲティング広告」などが、記憶の中の定着をサポートする施策です。
Action(行動)
最終ステップは、実際に消費者が行動を起こす段階です。
ECサイトでのカート操作、店舗での来店・購入、予約フォームへの入力など、物理的にアクションが起こることで売上につながります。
ここで障害になるのは「面倒くささ」や「不安」です。
スムーズなUI設計、簡単な決済方法、レビューの提示などが背中を押してくれます。
AIDMAの法則をビジョン策定に応用する

消費者の購買行動に関する理論に見えるAIDMAですが、実は企業のビジョン策定にも役立つ構造を持っています。
なぜなら、ビジョンは「企業が社会や顧客に対してどうありたいか」を発信し、共感や行動を促すコミュニケーションだからです。
AIDMAはそのまま、ビジョンの浸透プロセスとして活用することができます。
Attention:まず、ビジョンを「知って」もらう
社内外問わず、まずはビジョンを知ってもらわなければ共感も行動も生まれません。
Webサイトや採用ページ、社内研修、ニュースリリースなどを通じて、「こんな未来を目指している企業なんだ」と伝える工夫が必要です。
ここでは、ストーリー性や象徴的なキーワードが記憶に残りやすくなります。
Interest:興味を持たれるビジョンであること
単に「こういう理念です」と書いてあるだけでは、読まれて終わりです。
ターゲット(社員・顧客・取引先)にとって「それって私にも関係あるかも」と思ってもらえるよう、ビジョンの背景や理由、そこに至る過程を開示することが重要です。
たとえば「代表者の原体験」「社会課題とのつながり」などが興味喚起につながります。
Desire:この会社と一緒に未来を創りたいと思わせる
ビジョンの段階で強く意識すべきなのは、「共感」と「納得」。
それを読んだ人が「この世界を実現したい」「こういう組織で働きたい」と思えるようにすることが重要です。
企業ビジョンは感情に訴える力がないと、スローガン止まりになります。
デザイン、言葉選び、語り口調などの細部にも気を配ることで、心を動かすビジョンが生まれます。
Memory:常に思い出してもらえる仕組みづくり
せっかく響いたビジョンも、時間が経てば忘れられてしまいます。
そこで重要なのが「記憶化の仕組み」です。
たとえば、
- 日々の会議や1on1でビジョンに立ち返る問いを投げかける
- 評価制度や教育制度にビジョンを反映する
- 社内報や社外向け発信で定期的にビジョンを言語化する
などの取り組みが有効です。
Action:行動につながるビジョン設計を
ビジョンは「語るだけ」では意味がありません。
社員や顧客が「それなら、自分はこう動こう」と思えるような具体性を伴っていることが重要です。
たとえば、「地域のつながりを支える企業」というビジョンなら、社員が地域イベントに自主的に参加したくなるような導線や後押しが必要です。
顧客にとっても、「この企業の商品を買うことで社会課題解決に貢献できる」と感じられるような設計が求められます。
AIDMAはマーケティングだけでなくビジョンにも有効

AIDMAの法則は、単なる購買モデルではありません。
「人の心がどう動き、どう決断し、どう行動に至るのか」という、あらゆるコミュニケーションの原則を教えてくれるフレームワークです。
マーケティングはもちろん、組織文化、ビジョン策定、採用広報、営業戦略など、さまざまな領域に応用することができます。
弊社でも、様々な観点から機能するビジョンを策定していきます。
ぜひビジョンの策定方法でお悩みの方は、一度弊社にご相談ください。

株式会社comodo
石垣敦章(イシガキ ノブタカ)